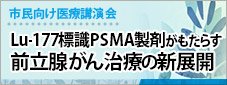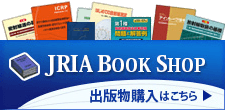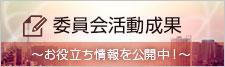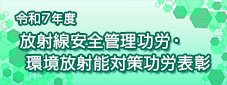| 文字サイズ: |
アイソトープ・放射線研究発表会 ポスター賞 受賞者のご紹介
本賞は、若手から中堅の研究者のキャリアパスを支援し、その研究活動を奨励することを目的として、アイソトープ・放射線研究発表会において優秀なポスター発表を行った者を表彰するものです。
第62回(2025年7月2日~4日)研究発表会の初回は22件の申込から6名が受賞され、表彰式には4名の方にご参加いただきました。
第62回アイソトープ・放射線研究発表会 「ポスター賞」
(会期2025年7月2日~4日)
| 受賞者(発表時の所属) | 演題(発表番号) |
|---|---|
| 授賞理由 | |
| 内田 海路 氏 (東京都立産業技術研究センター) |
有機塩基によるCO2捕集を用いた簡便なバイオベース炭素含有率測定(1P_E01-40-04) |
| バイオマス材料評価のため,簡便なバイオベース炭素含有率測定の手法を開発した。試料を燃焼し,発生するCO2をエチレンジアミンのエタノール溶液に通じ,カルバミン酸誘導体の白色沈殿を得た。粉末をすり潰した後,シンチレーションカクテルに混入し,C-14β線を測定した。参照物質から作成したバイオベース炭素含有率―放射能検量線は良い直線性を示した。様々なプラスチック製品から合成したカルバミン酸アンモニウムの放射能測定値と検量線から得たバイオベース炭素含有率は,加速器質量分析の結果ともよい一致を示し,本手法の妥当性が示された。発表内容の構成や質疑応答も高く評価できることから、本講演賞に値すると判断した。 | |
| 岡本 彩里 氏 (東京都市大学 総合理工学研究科 共同原子力専攻) |
散乱高エネルギー光子イメージングによる空隙移動検知の検討(1P_E01-40-16) |
| 放射線照射によるがん治療では,呼吸や腸内ガスの移動などによる腫瘍位置のずれを知ることは重要である。照射される腫瘍部位からの散乱γ線を測定することで,ガスなど空隙部位のモニタリングの可能性を検討した。人体を模擬するアクリルブロックを鉛でコリメートしたCo-60γ線で照射し,照射野の外に設けた空隙を1cm角から3cm角に変化させた際の45度,90度,135度方向の散乱線をγカメラで測定した。45度,90度方向においては空隙の大きさの変化が検知できることが分かった。発表内容の構成や質疑応答も高く評価できることから、本講演賞に値すると判断した。 | |
| 小山内 暢 氏 (弘前大学 大学院保健学 研究科) |
CT検査時における医療スタッフの介助状況 ~水晶体等価線量限度引き下げ前後の比較~(1P_E01-40-27) |
| CT検査時に医療従事者が患者の体位保持等のために検査室内にとどまることがある。2021年の法改正によって水晶体等価線量限度が引き下げられたが,引き下げ前(2020年4月)と後(2023年12月から翌1月)において撮影中の検査室への立入の有無,X線防護衣,放射線防護メガネの使用状況,個人線量計の装着状況等を調査した。立入と防護衣は前後で変化は少なく,それぞれ6割程度とほぼ100%であったが,防護メガネでは装着率が18%から63%に,不均等被ばく管理も35%から55%に改善した。発表内容の構成や質疑応答も高く評価できることから、本講演賞に値すると判断した。 | |
| 高取 沙悠理 氏 (岡山大学 異分野基礎科 学研究所) |
トリウム229アイソマーを用いた原子核時計の開発(1P_E01-40-12) |
| Th-229は例外的に低いアイソマー準位を有し,レーザーによる制御が可能であり,原子時計を上回る精度の原子核時計への応用が期待されている。励起には波長148nmの真空紫外レーザが必要であるが,適したレーザ媒質がないため,赤外と紫外パルス光をXeガス中で重ね合わせる4光波混合を行うことで,十分な精度と強度の光源を実現した。Th-229をフッ化カルシウム結晶にドープすることで一度に多数のTh-229を励起することが可能になり,新たに結晶場分裂の微弱なスペクトルの観測にも成功した。発表内容の構成や質疑応答も高く評価できることから、本講演賞に値すると判断した。 | |
| 濱口 裕貴 氏 (量子科学技術研究開発機 構 高崎量子技術基盤研究所) |
放射線架橋ゲルで解き明かす骨格筋線維タイプの移行を誘発する最適なメカニカル刺激(1P_E01-40-08) |
| 従来の硬い平らなプラスチック容器で培養した骨格筋細胞は,体内の細胞に比べ遺伝子の活性化が乏しく未熟で,筋線維のように整列しなかった。そこで生体コラーゲン由来のゼラチン水溶液にCo-60γ線を照射し,骨格筋と同程度の10~100kPaの柔らかさのゲルを作製した。また整列構造を再現するために幅3~50μmの縞状の凹凸構造を付与したゲルを作製した。10kPaのゲルで培養した骨格筋細胞は,ミオシンやミオグロビン遺伝子の発現が増加した。また凹凸構造は骨格筋細胞を整列させた。発表内容の構成や質疑応答も高く評価できることから、本講演賞に値すると判断した。 | |
| 福井 直樹 氏 (大阪健康安全基盤研究所) |
照射原料を用いた模擬加工食品の照射履歴検知の試み(1P_E01-40-39) |
| 食品照射が世界的に広く普及しており,厚労省から照射食品を検知する3種類の方法が通知されているが適用範囲が限局的である。普及率が高いタンデム型質量分析装置付き高速液体クロマトグラフを活用し,DNA中のチミジン(dThd)残基から生成する損傷ヌクレオシドである5,6-ジヒドロチミジン(DHdThd)残基を指標とする普及性の高い手法の開発を目指した。照射赤唐辛子を含有させた白菜キムチを模擬試料としてDHdThd/dThd比を算出したところ,含有率2%で検出可能であった。発表内容の構成や質疑応答も高く評価できることから、本講演賞に値すると判断した。 |